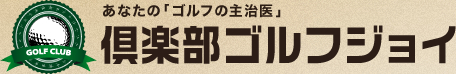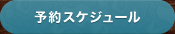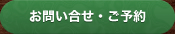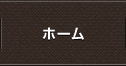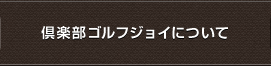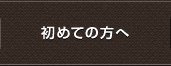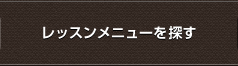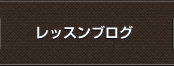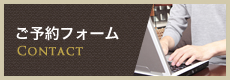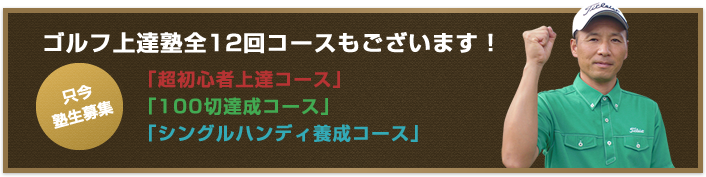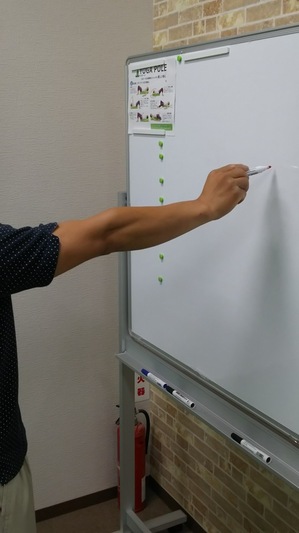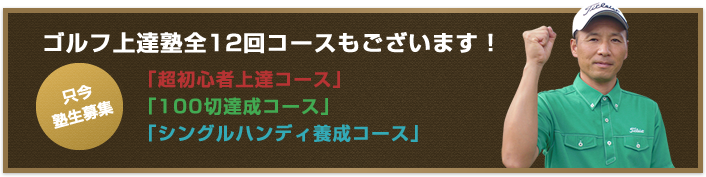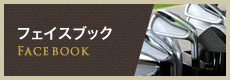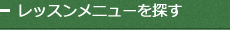メルマガ記事
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法36
ショットの方向性をアップさせ、安定させるには?
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
練習場では、まあまあ方向性も安定しているし、そんなに曲がらない。
「よし、これで次のラウンドはバッチリだ!」と思ってコースに出てみたけれど…。
練習場では良くても、ラウンドでは球が曲がってしまったり
安定しない理由は、大きく分けて2つあります。
その2つの理由の1つ目だけでもクリアできれば、
ショットの方向性と安定感は、見違える程良くなるでしょう。
1つ目の理由
「球に対して構えるから」
ショットの安定性を無くし、方向性を悪くしたり、
大きく曲げてしまう1つ目の理由は、アライメントと言われる方向取りのエラーです。
つまり、目標に(真っ直ぐに)平行に立てていないということです。
その原因は、「球に対して構えている」からです。
球に対して構えていては、目標に平行(真っ直ぐ)に立てる確率は低くなります。
では、何に対して構えれば良いのでしょうか?
続きはこちらで ⇒ ポイント1/ポイント2/ポイント3/ポイント4
2つ目の理由
「メンタルのコントロール不足」
一口にメンタルと言っても、具体性に欠けるでしょう。
大きく3つに分けてみます。
① 自意識
例えば、「他人に見られている」と意識してしまうと、結構動きがギコちなくなってしまうものです。
ふだんの練習から、「常に他人に見られている」と意識しながら練習していきましょう。
他人の視線に”麻痺する”くらいになりたいところです。
実は、他人って、あなたが意識しているほど見ていないものなんですが・・・(笑)。
② 雰囲気
特に久しぶりのラウンドだと、高揚感や緊張で、我を失っているものですね。
俗にいう「地に足がつかなくなる」ことでしょう。お腹と内ももにグッと力を込めると、
地に足がつき、周囲を見渡せる余裕も生まれてきます。
③ レイアウトによる制限
ティショットでは、左サイドにOB、右サイドは池と逃げるエリア無し。
2打目は、グリーンの左はバンカー、右はガケなどと、「制限」がかかると、
スイングがきゅうくつになってしまいます。
ぜひ、前述の1つ目の理由をマスターして克服してください。
さらに、スイング動作の改善点や課題を3つ挙げます。
これらが主な練習課題となります。
3つの改善点(課題)
① トップとフォローの位置
② 前傾姿勢がキープできる目線の作り方
③ ボディターン
以下の練習ドリルも併せて実践すると、より効果的です。
了
千葉、茨城、埼玉、関東近辺で実施しています。
※ 料金体系はこちら → クリック ※ お申込み4W1H一覧表はこちら → クリック
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法35
バットのブンブン素振りで、バンバン飛ばそう!
~ジムで筋トレしなくても簡単に飛距離アップできる~
最近、練習場やゴルフ場のスタートホールで、バットで素振りしている人をよく見かけます。
バット素振りは、スイング作りや準備体操にとても有効なので、オススメです。
では、一体どんな効果があるの?
なぜ、バット素振りが効果的なのか、理由を3つ挙げてみます。
① バットは、クラブより重いので、踏ん張る意識が強くなり軸ブレが少なくなる。
② 筋肉に負荷がかかるので、筋トレにもなり、ヘッドスピードアップにつながる。
③ 練習前やスタート前に、ゆっくり素振りすることで、ストレッチ効果がある。
道具を使うスポーツは素振りが大事です。
野球、テニス、剣道、卓球等、素振りが大変重要視されていますし、
その分野の選手は、毎日素振りをしています。
正しい振り方を教えて!
ゴルフショップなら必ず売っている、
グリップが装着されたバットを購入していただくことを推奨します。
5000~6000円とやや高価ですが、お値段異常の効果はあります!
アイアンの7,8,9番の2、3本をわしつかみにしてスイングしても、
同様の効果があるでしょう。1本はグリップとヘッドを逆さまにして持つと、
重量配分が適正になります。
⚫ まずは、水平にビュンビュン振ってみましょう。
徐々に地面に近づけていき、通常のスイングのような素振りをします。
⚫ 5回を1セット、10回を1セットで素振りしてみましょう。5回素振りなら、1振り目はゆっくり、
2振り目は少しスピードを上げて、5回目は思い切りスピードを上げます。
⚫ 左スイングも同様同回数振ることで、バランスの取れたスイングになります。
余談ですが、笑いながら素振りすると、筋肉が硬直しないので、速く振れるます。
試してみてください。ヘッドスピードアップに効果がありますよ!
バット素振りは、飛距離アップに大変有効なため、キャディバッグに入れておきたいものです。
ただし、コンペや競技のラウンド中の使用はルール上NGとなりますので、使用はスタート前までです。
しかし、プライベートラウンドでは、そこまで堅苦しく考えることはありませんから、どんどん使用してみてください。
千葉、茨城、埼玉、関東近辺で実施しています。
※ 料金体系はこちら → クリック ※ お申込み4W1H一覧表はこちら → クリック
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法24
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
バックスイングは肩をしっかり回すな(その2)
(その1)のつづきから
☆★上達につながる正しい理解☆★
ではどうやって、
“飛んで曲がらない”
バックスイングを作っていけば良いのでしょうか?
バックスイングは、肩ではなく、腰や太ももからねじっていけば、
肩は“自然に”回ってきます。
腰は、「肩の周りの半分」を目安にしましょう。
つまり、肩は「回す」のではなく、
肩は「回る」
のです。さらには、肩は「回ったように見える」という方が
骨格的には適正な表現でしょう。
1.良いバックスイングの形
2.腕で引っ張り上げて肩を回した形
両者のバックスイングの形を比べてみると、
上半身のリラックス度の違いは明確にわかります。
肩の回転量は、90度~110度くらいが理想と言われていますが、
柔軟性に乏しい方は、70度前後、柔軟性がかなり低い人なら
45度位でもいいでしょう。
無理に肩の回転を得ようとして上半身が力むよりも、
45度でも十分な肩の回転量と私は見なしています。
肩を回すことより、フットワークを上手に使うことです。
バックスイングでの右ひざは
しっかり曲げたまま、左ひざを右ひざに寄せながら、
腰は45度くらい右に向けましょう。
身体が硬い人は、左足かかとを少し浮かせるといいのです。
きれいに背中が目標に向き、自然と肩が回ってきます。
肩の回転量が少なくても、前定説の、
「バックスイングでは、左腕を真っ直ぐに伸ばす」
でお話したように、左腕に十分ゆとり(曲げて)を持たせていれば、
ダウンスイングからインパクトにかけて、ラクに振り抜けていけます。
※ 左ヒザの使い方に注目してください。
≪良いバックスイングの作り方≫
1.右のポケットを後に引かれるイメージ
2.背中を目標に向けるイメージ
だと、スムーズにバックスイングできます。
ちょっとしたイメージや意識の持っていき方で、
身体をラクに使うことができます。
≪ 上手にバックスイングできるリュックサックドリル ≫
バックスイングを手先で引っ張り上げて肩を回していたゴルファーに、
おススメの練習法をご紹介しましょう。
リュックサックを背負ってスイングしてみると、
手先ではない、ボディターンのバックスイングのフィーリングがつかみやすいです。
適度な重さのモノを詰めてください。
肩に意識を持っていかず、フットワークを主体にして、
バックスイングでは、リュックサックを左に、
ダウンスイングで右に揺すってみてください。
背中側に意識がいくので、小手先ではなく、
大きな肩の回転が得られるイメージがつかめるでしょう。
<今回のまとめ>
バックスイングでの肩は、
“回す”のではなく“回る”
または、“回ったように見える”
肩ではなく、下半身や背中に意識を持っていくことで、
スムーズに肩が回ったバックスイングになる。
つまり、バックスイングで「肩を回す」とは、ヒザや股関節で身体をねじることである。
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法41
体重移動はするな
と表現されれば、いかにも飛ばせそうなイメージが湧いてきます。
ここが我流スイングへの落とし穴だった!
左右に使うのは体重移動を直線運動とカン違いしていて、
前後に使うのは股関節の可動域が狭くて正しく動かせないか、
ゴルフ特有のヒザの使い方を理解していないかのどちらかです。
自分流スイングへの転換のコツ
「大きな体重移動をしよう」と、スタンス幅を広くとると、
どうしてもスムーズな回転運動はしにくく、
横方向に動きやすくなってしまい、軸もブレやすくなります。
千葉、茨城、埼玉、関東近辺で実施しています。
※ 料金体系はこちら → クリック ※ お申込み4W1H一覧表はこちら → クリック
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法39
ミート率を上げたければ、スイング中の手足は短く使え
飛距離とミート率の関係
ここが我流スイングへの落とし穴だった!
正しい解釈へのポイント
自分流スイングでの腕の使い方は、交互折りたたみ式に
千葉、茨城、埼玉、関東近辺で実施しています。
※ 料金体系はこちら → クリック ※ お申込み4W1H一覧表はこちら → クリック
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法38
フォロースルーは大きくするな
3.「~する、しよう」
ここが我流スイングへの落とし穴だった!
遠心力を考慮しなければ、円と直線がケンカしてしまう
自分流スイングへの転換のコツ
正しい解釈へのポイント
千葉、茨城、埼玉、関東近辺で実施しています。
※ 料金体系はこちら → クリック ※ お申込み4W1H一覧表はこちら → クリック
 クリック!
クリック!
「競技ゴルファー、シングルプレーヤー養成レッスン」のご案内 → クリック
千葉、茨城、埼玉、関東近辺で実施しています。
※ 料金体系はこちら → クリック ※ お申込み4W1H一覧表はこちら → クリック
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法37
ダウンスイングは「インサイドから下ろせ」の正しい理解
ここが我流スイングへの落とし穴だった!
アンコックやボディターンといった他の必要な動作と組み合わないと、
結果的にタメをほどかなかったことと同じことになり、
右に飛び出して右に曲がる、OB続出の最悪のプッシュスライスの原因になっています。
開いて下りてきて、大きく右に飛んでいくことになる、
我流スイングへと陥ってしまったのです。
自分流スイングへの転換のコツ
ダウンスイング8時の位置でも、クラブヘッドとシャフトが
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法33
スイング中は球を凝視しないで頭を動かせ
ここが我流スイングへの落とし穴だった!
自分流スイングへの転換のコツ
自分流スイング作りでは、「バックスイングで頭は動くべき」とする
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法32
スイング軌道は目標方向、後方への直線の動きはない
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法31
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
アプローチの距離感向上は、旗をオーバーさせること
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法30
アプローチは、手首を固定しようとするな
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法29
「飛距離をアップさせたい!」なら、コンパクトなトップにしろ
さらに食事管理まで徹底し、身体のコンディションを相当高いレベルで保っています。
≪ここが我流スイングへの落とし穴だった!≫
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法28
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
フェアウェイウッドが上手くなる方法
飛距離不足に悩んでいるはゴルファーは、
フェアウェイウッドを使いこなせるかどうかで、
スコアメイクに大きな差が出てくることを充分に実感していることでしょう。
特に女性ゴルファーは、飛距離が出ない方が多いため、
フェアウェイウッドを打ちこなせるとプレーがラクになります。
といって、「ではすぐに使ってみましょう」とはいかないのがゴルフですね。
狭いホールでは、ティショットでドライバーを使うのを止め、フェアウェイウッドで攻めることで、リスクを大きく減らすことができます。
パー4、パー5のティショットは、常にドライバーという考えを変えてみてもいいでしょう。
確実に大叩きは減るはずです。
ドライバーが不安で怖い場合は、ティショットで
フェアウェイウッドを代用すれば大きなミスを防ぐことができます。
リスクはドライバーよりもかなり少なく、
OBも減り100切り達成にグッと近づきます。
さあ、今回のお話を参考にして、フェアウェイウッドをコースで打ちこなしてください。
《フェアウェイウッドの機能や特長、使い方を知ると、ミスしなくなる!》
フェアウェイウッドは、ソール面積がアイアンよりも広く、
ダフりに強い形状になっています。
だから「滑らせるように打て」「ダフってもいい」と言われています。
ふつうは、ダフることはミスだと思ってしまうでしょう。
フェアウェイウッドはソールの面積が広いため、
インパクトで少々ダフっても、滑って振り抜けてくれます。
だから、ダフリを怖がってスイングすることはありません。
クラブの機能を知っておくだけで、ミスに強くなれます。
フェアウェイウッドは、シャフトが長いので、
スイング軌道はフラット(横振り)になってインパクトゾーンの入射角度も浅くなります。
フェアウェイウッドのクラブヘッドが地面を滑りやすくなる条件がそろっています。
フェアウェイウッドの正しい機能や特徴、使い方を知ると、発想が180度変わるでしょう。
最初から「軽くダフってもいい、構造的にはダフりにくいのだから」くらいに思って打てば、
失敗の不安が軽減されて思い切ってスイングできます。
ヘッドスピードが落ちることなく、芝の上をスルっと滑って振り抜けてくれます。
今までの「失敗」(に見える、そう思っていた)を、
「技術」にするゴルファーと、
「失敗」としか考えない(視点が狭く、知識不足)ゴルファーとでは、
1打に大きな差が出るのです。
《発想の転換でミスショットをナイスショットに変えてしまえる》
「ダフっていけない!」と思ってダフれば、
ためらってヘッドスピードが落ちたり、軌道がゆがんだりします。
または、相当鋭角な軌道(入射角)でインパクトしようとするので、
もし本当にダフれば地面に刺さってしまいます。つまり大ダフりです!
仮にダフらなくても、鋭角な入射角でしかインパクトされないので、
かなり低い弾道になってしまいます。こんな失敗の連続が、
ますますフェアウェイウッドの自信を失わせてしまいます。
フェアウェイウッドは、少々ダフってもいいと思って打つと、
少しくらいのダフりなら、本当に地面を滑ってミスにならないのです。
《3番ウッドが使いこなせる条件》
よく質問されるのが、
「2打目で、3番ウッドはどうすれば打ちこなせるか?」
ということです。
ドライバーの次に飛ばせる”可能性”のあるクラブですから、この質問は最もなことです。
フェアウェイウッドが打ちこなせる条件として、
1.ある程度のヘッドスピードがあり、
2.適正なスイング軌道の理解と技術を身に付けていること
が挙げられます。
3番ウッドを、2打目以降で地面から(ティアップしないで)打ちこなすには、
かなりのヘッドスピードと正確なスイング軌道が必要になりますから、
現時点で条件が満たされてないゴルファーは、
残念ながら3番ウッドの使用を見合わせましょう。
1.の「ある程度のヘッドスピード」とは、
ドライバーのヘッドスピードが40以上出せているかどうかです。
もし未満なら、3番ウッドではドライバーの次の飛距離を出せないでしょう。
しかし、3番ウッドをティアップして打てば、難易度が5番ウッド並になってきます。
現時点で3番ウッドを打てないゴルファーは、
パー3またはパー4のティショットから使っていくのをお勧めします。
2.は、ダフったりトップしたりしない、大きく曲げない、
といったスイングの基本的な技量とスイング理論の理解があることです。
3番ウッド→5番ウッド7番ウッド→9番ウッドになるにつれて、
ヘッドスピードと技量のレベルダウンがOKとなってきます。
《番手によってどのくらい飛距離が落ちるのか》
私は、フェアウェイウッドが苦手なゴルファーには、
2打目以降に使うクラブは5番ウッド以下にしましょうとアドバイスします。
7番ウッド、9番ウッドから取り組んでみてもいいでしょう。
5番ウッドや7番ウッドは、3番ウッドに比べると
かなり飛距離が落ちてしまうと思っていませんか?
実は、5番ウッドなら、飛距離は3番ウッドとそんなに大きく変わらないものです。
3番ウッドが苦手な人なら、5番ウッドの方がむしろミート率は高く、
球も上がりやすく圧倒的に打ちやすいので、
トータルでは3番ウッドに比べて飛距離は変わらないか、負けないでしょう。
7番ウッドや9番ウッドは、数字が大きいので飛ばないイメージがありますが、
3番ウッドと7番ウッドでは、飛距離の対比は、10:8くらいです。
ヘッドスピードが速くない方なら、むしろこの比率が逆転することがあるでしょう。
こういう知識を持つことでも、ウェイウッドでのミスを減らせるのです。
《フェアウェイウッドの構え方と打ち方》
アイアンの構え方からアレンジしていきます。
まず球の位置ですが、
「スタンスの中央に何を置くか」
で決めていきます。(アイアンとの対比)
アイアンの場合は、スタンスの中央に球を置きますが、
フェアウェイウッドはスタンス中央にヘッドを置きます。
結果的に球はやや左寄りになります。
スタンス幅は、アイアンよりやや広めでいいでしょう。
特別に広くしないしないことをおススメしまします。
苦手なクラブは、スタンス幅は狭めの方が、確実にミスは減らせます。
アイアンもフェアウェイウッドも打ち方は同じです。
フェアウェイウッドは、アイアンよりも
低い飛び出し角度をイメージしてください。
飛ばしたいときは、どうしても高く打ち上げたくなるが、フェアウェイウッドは、ロフト角はアイアンより低いので、打ち出し角度は、アイアンより低くイメージしましょう。
球の右側を見てインパクトすると、適正な打ち出し角度が得られます。
アドレスで軸が右に傾くので、球のやや右側を見てスイングすると、
番手なりの高さが出せるようになります。
そして、必ずフィニッシュを決めることです。
ラウンドでは、まずは苦手意識を取るために、
フェアウェイからでもティアップして進んでいくといいでしょう。
朝の練習場では、ティアップして、通常出せ得る距離の半分から打っていくと
効果的なウォーミングアップができます。
《正しい理解のポイント》
私の印象では、フェアウェイウッドが
苦手な人ほど、飛距離も方向性もと欲張って、
最高の結果ばかりイメージしているようです。
まずは、自分の技量に合った番手を選び、
まあまあの距離から打っていくことから始めます。
例えば、ナイスショットで180ヤード飛ぶなら、
最初は150ヤードからで良し、といった具合です。
「打ちこなそう」や「飛ばしたい」から、
まずはフェアウェイウッドが「嫌いではなくなった」
「まだ上手くはないけど、苦手意識は薄らいだ」を目指しましょう。
ライが悪かったり危ない状況だったりしたら、
3ウッド→5ウッド→7ウッドの順に下げていき、
さらには、アイアンを使うといった、
潔く目標を下方修正できる判断力も必要です。
つまり、場面や状況によって
フェアウェイウッドを使うのを控えるのも、立派な選択であり、
そういう考え方も打ち方の技術と同等以上に必要なのです。
無理にフェアウェイウッドを使って大惨事になり、
「あー、やっぱ使わなければよかった!」
とならないためにです。
プロでも無理な場面や自信がない状況では、
ウッドをアイアンに下げて狙います。
<まとめ>
■フェアウェイウッドは、ダフりに強く、キレイに打とうとしなくても
クラブヘッドのソールを滑らせるように打てば、ラクに打てる。
■ドライバーのヘッドスピードが40以下、200ヤード未満の飛距離の人は、
3番ウッドよりも5番ウッドがおススメ。
■フェアウェイウッドの構えは、アイアンの構え方を基準に変化させていく。
■場面や状況によっては、フェアウェイウッドを使わないのも選択肢。
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法27
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
ウッドとアイアンは同じスイングなのか?
「アイアンは打ちこんで打つ」
「ウッド系は払うように打つ」
と、よく耳にしますね。
さらに、アイアンは「タテ振りに」、
ウッド系は「横振りに」も、
定説のように”表現されています。
何か、打ち方の区別が必要なようにも聞こえてきますが、
なぜこのような定説が生まれたのでしょうか?
アイアンとウッドでは、長さも形状も打感も違います。
だから打ち方を変えるのでしょうか?
本項目の疑問を解決していくにあたって、
① 「スイング軌道」
② 「ライ角度」
③ 「前傾角度」
というスイング理論に関する3つの用語をキーワードとして考えていきましょう。
これらの理論の理解と実践ができれば、シンプルにスイングができるようになります。
応用として、傾斜地からの打ち方にも大きく役立ちます。
《3つのスイング理論の理解》
まず「スイング軌道」からお話します。
クラブヘッドが描く軌跡のことで、
■ インパクトのヘッドの位置をスイング軌道の最下点
■ トップと左右対称のフィニッシュの少し前くらいのヘッドの位置(同一)をスイング軌道の最上点
とし、その2点を結ぶ傾きのある円軌道のことです。
スイング軌道を「横振り、タテ振り」と表現するのは、
使用クラブの変化によって、スイング軌道の傾きが、
より水平に近くなるか、より垂直に近くなるか、という意味です。
短いクラブになっていく程、身体と球との距離が近くなっていくので、
スイング軌道の最下点も身体に近くなり、最上点と結べば、
スイング軌道の傾きはより垂直に近くなっていきます。
これが「タテに振る」感覚と言えるでしょう。
アイアンのスイング軌道の傾き
ドライバーのスイング軌道の傾き
逆に長いクラブになっていく程、身体と球との距離が長くなっていくので、
短いクラブよりスイング軌道の傾きは、より水平に近くなっていきます。
これが「横に振る」感覚と言えるでしょう。
アイアンは、ウッドよりシャフトが短いので、よりタテに振る感覚になり、
「打ち込んでいる」イメージが生まれるのだと考えられます。
次に「ライ角度」を知りましょう。
適正なライ角度とは、クラブヘッドを平らな地面に、
極端に先端(トゥ)や付け根(ヒール)の片方が浮かないように置いたときに、
地面とシャフトとの間にできる角度のことです。
地面に引いてある赤い線とシャフトとの間にできるのが、ライ角度です。
画像では、わずかにしか見えませんが、構えている人からは、
アイアンとウッド系では、かなりライ角度が違う感じがします。
最後に「前傾角度」です。
ウッド系はクラブが長いので、前傾角度は浅めになり、
アイアン系はクラブが短くなるので、前傾角度は深めになります。
ウッド系からアイアン系にかけて、
クラブが短くなるにつれて前傾角度は深くなっていきます。
各クラブの適正なライ角度に沿って構えれば、適正な前傾角度で構えられます。
前傾角度が適正よりも深過ぎると、クラブヘッドのトゥ側が浮き過ぎてライ角度が狂い、
スイング軌道は横振りになってしまいます。
バックスイングでフェースが大きく開いてしまったり、
スイング軌道がインサイドに入りすぎたりして、
弾道は大きくスライスしてしまうでしょう。
それを警戒して、インパクトで急激にフェースを返すと、
強いフックボールになり、球筋はなかなか安定しません。
逆に、前傾角度が適正より浅過ぎると、
クラブヘッドのヒール側が浮き過ぎてスイング軌道はタテ振りになってしまいます。
バックスイングでフェースを閉じてしまい、
急激にアウトサイドに上がりやすく、弾道は低く左に飛びやすいでしょう。
これらの理論を理解すれば、スイング軌道はクラブの長さに応じて、
自然に適正な傾きのスイング軌道になっていくことが実感でき、
タテ振り、横振りという感覚も自然に感じられることでしょう。
理論を知らずに、定説にまどわされていれば、我流スイングのままで、
安定しないショットに苦しむことになってしまいます。
《スイング軌道の変化を感じていく》
100切り達成スイング理論では、アイアンのスイングを基準とすることを提唱します。
なぜなら、ショットは、芝の上の球をティアップなしに、
直接打つことの方が圧倒的に多いからです。
スイング軌道、ライ角度、前傾角度の理論を理解したアドレスとスイングならば、
全クラブのスイングがそろってきて、安定したショットが打てるでしょう。
ウッド系は、アイアンよりも球を左寄りに置き、スタンス幅も広くなります。
軸をアイアンより右に傾けて構えるので、自然に「払うように」インパクトされます。
アイアンは、球の位置は真中付近になり、ほぼ真上から見るようになるので、
自然に「上から打ち込むように」インパクトされます。
「上から打ち込むようにインパクトする」の意味ですが、昨今のクラブでは、
単純に「ダフらないようにインパクトする」と理解するだけでいいでしょう。
スイング軌道を把握し、適正なライ角度と前傾角度で
各クラブの長さ別に応じて構えていけば、スイングは変えていくのではなく、
変わっている感じがする、というのがスイング作りの考え方です。
また、アイアンとウッドではヘッド形状も打感が違うので、
スイングが違うと感じてしまうかもしれません。
しかし、クラブの長さの変化によって、
スイング軌道、ライ角度、前傾角度を含んだ構え方(スタンス幅や球との間隔)は、
一定の度合いで変化していきますが、
スイングの動作自体は一つにするのがスイング作りの理想です。
《傾斜地ショットへの応用》
「スイング軌道」、「前傾角度」、「ライ角度」の理論が理解できると、
傾斜地ショットに応用していけます。
また、スイング理論の理解度が傾斜地からのショットの出来具合で計れます。
前傾角度とライ角度は、左右ではなく前後に変化するので、
「つま先上がり」と「つま先下がり」で応用していきます。
「つま先上がり」の傾斜地では、球が平地より上にくるので、
スイング軌道の傾きは平地よりも水平に近づきます。
ライ角度は、トゥが上がってしまいフェースが左を向くことになるので、
ボールは左に曲がりやすくなります。
よって、前傾姿勢は平地よりも浅くし、クラブを短く持ちます。
クラブを短く持てば、トゥが上がってしまったライ角度を補正でき、
平地から打つ角度と同じにすることができます。
しかし、足場は平地に比べてバランスが悪いので、
半分から7割くらいまでのスピードでスイングする方が安全です。
「つま先下がり」の傾斜地では、球が平地より下にいくので、
スイング軌道の傾きは平らな地面よりも垂直に近づきます。
ライ角度は、トゥが下がってしまいフェースは右を向くことになるので、
ボールは右に曲がりやすくなります。
よって、前傾姿勢は平地よりも深く構えます。
クラブは短く持つと、ますます球に届かなくなるので、平地と同じ長さで持ちましょう。
ライ角度の補正はあまりできません。
つま先下がりの場合
つま先上がりの場合
傾斜地では、脚力とバランスに自信がないゴルファーは、
平地の半分くらいの距離で良しとしましょう。
傾斜地からナイスショットが打てるようになれば、
スイング理論は身体と頭の両方で、かなり深く理解していることになり、
平地からのショットの安定感はさらに増すでしょう。
≪まとめ≫
アイアンはクラブが短いので、スイング軌道がより垂直に近づき、
タテに振る感覚になり、ウッドはクラブが長いので、
スイング軌道がより水平に近づき、横に振る感覚になるのだと述べてきました。
「3つのスイング理論」でご理解いただけると思います。
100切りが達成できるスイング作りでは、
アイアンのスイングを基準とすることを提唱します。
スイング軌道、ライ角度、前傾角度の理論を理解し、
さらに球の位置やスタンス幅の変化、軸の傾きを
一定の度合で変化させていったアドレスとスイングならば、
全クラブのスイングがそろってきて、
スイングの動作自体は一つにするのがスイング作りの理想です。
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法26
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
スムーズなバッスイングの上げ方
皆さんは、アドレスが決まり、
バックスイングを始める直前では
どのような状態でしょうか?
アドレスでじっとしたまま、
なかなかバックスイングを始めない
ゴルファーが多いようですね。
本人は、クラブを上げるきっかけを探しているのか、
集中力が高まるのを待っているのか、
または不安や心配と戦っているのか、
見ている側では見当はつきません。
さあ打とうと構えても、
① なかなかバックスイングを上げられない
② モジモジ固まってしまう…。
③ 練習場ではスムーズに上げられるのに…。
上級者やプロは、流れるようにスムーズなバックスイングをしている。
自分は、なぜスムーズにクラブを上げられないのか・・・。
そんなお悩みを持ったゴルファーは多いことでしょう。
≪なぜバックスイングが上がらなくなってしまうの?≫
主な原因として、
「これから打つショットが失敗するかもしれない」
という不安で動作が固まってしまい、
バックスイングをスムーズに上げられないものと考えられます。
誰しも、失敗するためにスイングはしたくないはずです。
こんな感情が高まると、スイングしようとすると意図する動きができなくなってしまう
”イップス”
というゴルフの病にかかってしまうと言われています。
一番神経を使うパッティングに多いと言われていますが、
ショットやアプローチでも、このイップス症状になってしまう人がたくさんいます。
失敗も成功もたくさん経験してきている、
比較的経験豊富な上級者に多いようです。
≪緊張を和らげ、リズムを取るために小さく動いている≫
イップス症状は、強く緊張する場面にのみ訪れます。
何球でも打てる練習場では、あまり緊張もしないので、
バックスイングもスムーズに上がっていき、思い通りの動きができるのです。
しかし、コースまたは試合などの
「結果を出さなくてはならない場面」
では、突然イップスが顔を出し、多くのプロ選手も悩んでいると言われます。
イップスとまではいかないまでも、誰でも完全に静止した状態から動作を始めると、
動き(バックスイングの始動)にムラやブレが出やすくなります。
ゴルフは止まっている球を打っていきますが、
他の多くの球技は動いている球に反応しながら打っていきます。
テニス、野球、卓球、その他、球が飛んでくるのを待っている間は、
プレーヤーは無意識でリズムを取りながら、小刻みに動いているはずです。
先に述べたように、ゴルフスイングは、止まった球を打っていくため
完全に静止した状態から動作を始めると思われがちです。
しかし、いったん静止してしまうと、身体が硬直してしまうことが圧倒的に多いのです。
≪バックスイングの始動のきっかけを作ることで、ナイスショットの確率を上げる≫
バックスイングを上げる直前まで、完全に静止する時間を極力無くしましょう。
バックスイングを始める直前に、ちょっとした、
“きっかけ”
動作を入れると、身体が硬直せず、スムーズにクラブが上がっていくものです。
テレビ等で、プロの選手のアドレスからバックスイング直前をじっくり観察してみてください。
ほぼ全員の選手が、固まらず小刻みに動いていることに気付くことでしょう。
あれは、意図的に行っているのです。
スイングを成功させる秘策は、
バックスイングの直前まで静止せず、始動のきっかけの動作を取り入れることです。
このテクニックが上手いゴルファーは、イップスにかかりにくいでしょう。
もちろん、100切りを目指すアベレージゴルファーにも、
ぜひとも身につけてもらいたいテクニックです。
スイングは、
「静止状態から動き始める」
のではなく、
「微動状態から動き始める」
のが、ナイスショットを生む秘訣なのです。
静止せずに小刻みに動くことで
身体の硬直を防ぎ、不安や緊張を跳ねのけることができるようになるのです。
では、ナイスショットの“きっかけ”を作る具体的なやり方をご紹介します。
≪スイングの始動のテクニックの例≫
アドレスでじっとして固まってしまうゴルファーに名手はいません。
このスイングの始動のテクニックを会得すれば、
緊張や不安でスイングがブレてしまうのを防げるでしょう。
イップスのゴルファーに聴いてみると、
「止まっている球にクラブヘッドを正確に当てるために、
ピタッと静止して集中力を高めている」
と、教えてくれました。
一見、最もに聞こえますが、
前述したように、緊張で身体が硬直しやすく、
ミスの確率が高まってしまいます。
しかしどうしても静止してしまうという人もいることでしょう。
「静止状態は最大2秒まで」
と覚えておいてください。
2秒以上静止してしまうと、硬直が始まり、不安や恐怖心が
湧きおこってきやすいと言われています。
以下の、「上達につながる正しい理解と実践」で
「きっかけ動作」
の例を挙げておきます。
☆★上達につながる正しい理解と実践☆★
バックスイングのスムーズな上げ方について、
効果や考え方をまとめてみました。
下半身でスイングをリードできるイメージがつかめ、手打ちの防止になります。
少しおおげさに感じるくらいに動いてみましょう。
この動作自体に意識が行ってしまい、最初は上手くいかないかもしれませんが、
まずは、素振りでコツをつかんでみてください。
■ 「怖さを感じないように」ではなく、
「怖くてもナイススイングできるように」プレッシャーに強くなる。
■ スイングレベルを上げるのではなく、
現時点でできる一番良いスイングを発揮できるように。
■ 人は怖いときには、動いている。
動いていると、不安や恐怖感が入ってきにくい。
日常生活でも、深く考えている状況では、
動作は完全に静止しているものでしょう。
ゴルフでの緊張する場面や強いプレッシャーがかかる状況で
“思考力が高まる”
と、よほどの上級者でもない限り、
「不安や失敗するイメージ」が湧いてくるのではないでしょうか。
<今回のまとめ>
「ナイススイングは、良い始動から生まれる」
ゴルフスイングは、完全に静止した状態から動き出すと、
始動にムラやブレが出るものとお話してきました。
バックスイングは、「静から動」ではなく、
「微動から動」というイメージが、
一番滑らかにクラブヘッドが上がっていきます。
人間は、完全に静止してしまうと、思考力が高まると思われます。
ということは不安や失敗するイメージが湧いてくるのです。
静止せずに小刻みに動いていると、
思考力の働きが抑えられ、プレッシャーを感じにくくなるでしょう。
また、プレッシャーを感じても、
意図する身体の動きができるようになるでしょう。
最初は、この動作自体に意識が行き過ぎて、
上手くいかないかもしれませんが、
意味や効果を理解して反復練習すれば、
このテクニックの効果を必ず実感できます。
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法25
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
「ワキを締めてスイングする」の真意
「ワキを締めてスイングしろ」
練習場で、ゴルファーの練習風景を見ていたら、
ヘッドカバーやバスタオルをワキにはさんで、
落とさないようにスイングしている人がいます。
とても熱心な方なのでしょう。
ただ漫然と球を打つのではなく、練習に工夫が見られ、
上達したいという気持ちが伝わってきます。
ワキにヘッドカバーをはさんで練習するドリル
しかし、よく見ていると、
ワキにモノをはさんだままフルスイングの練習をしているのです。
このドリルは、肩から肩までのハーフスイングで実践するのですよ、
とお伝えしたかったのですが、その勇気がありませんでした(笑)。
ほとんどのゴルファーが、“ワキを締める”というと、
「ワキをぴったり閉じる」
と思っているようです。スイング中のワキは、
“空間を作ってはいけない”
ということでしょうか?
「ワキを締めて振れ」の表現をそのまま解釈すると、
確かにそう受け取ってしまいそうです。
しかし、プロのスイング写真を見ると、
トップやフィニッシュでは、ワキに空間があるように見えます。
下の画像で、ヒジとワキのスペースに注目してください。
「空く」といっても、エラーの空きと、
必要かつ適正な空きの違いを理解しておきたいです。
スイング中のワキの空き具合を比較してみましょう。
実は、「ヒジをたたむ」ということに、
この項目の正しい理解へのヒントが隠されています。
関連する表現として、
「スイング中は三角形を崩さない」
があります。これら二つの表現を一緒に見ていくことで、
誤った解釈でワキを締めた変則スイングから脱却できるでしょう。
☆★“その定説”を徹底検証する☆★
ワキを締めることを誤解しているゴルファーは、
スイング中、ずっとワキを締めようとしているようです。
これでは、ワキが“締まる”が、“縮こまる”ことになり、
適正なスイング軌道から大きく外れてしまいます。
「ワキが空く」正しい空間を明確にしておくことです。
先に述べたように、ワキにヘッドカバー等をはさんで、
スイング中に落とさないように練習しているゴルファーを見かけますが、
正しい意味とやり方を理解していないと、逆効果になってしまいます。
バックスイング9時の位置以降は、
ワキにはさんだモノは、むしろ落ちなければなりません。
ダウンスイング9時からフォロースルーにかけては、
またワキは締まってきますが、もちろん意図的に締めようとするのはNGです。
この練習法は、腕の動きが9時から3時の位置までで、
フルスイングはしないのが正しい練習法なのです。
これでは、ワキを締めるより”縮こまって”しまいます
ワキの締まり具合の目安が案外難しいようですね。
スイング中、終始ワキを「空けてはならない」のではなく、
「スイングの途中までワキが締まっている」
というのが正しい解釈です。
トップ・オブ・スイングとフィニッシュの位置では、
ワキにわずかな空間ができます。
スイングではこれを「ワキが空く」とは言わず、
「正しく必要な空間」
と考えます。
スイング中の両肘は真下を向いていればOK
≪ナイススイングへの転換のポイント≫
良いスイングは、アドレスの段階でワキはすでに締まっているのです。
スイング中に、ワキを
「締めようとする意図」
は不要であると理解してください。
静止している状態ですから、良いアドレスの真似はできることでしょう。
良いアドレスに関しては、柔軟性等の身体的個人差はほとんど関係ないと思われます。
正しい知識と理解が、良いスイングへのアレンジのコツです。
私が考えるスイング理論では、バックスイングでの左腕が9時~10時の位置付近では、
右肘はほぼ真下に向き、フォロースルーでの右腕が3時~2時の位置付近では、
左肘がほぼ真下を向いていれば
「ワキが締まっている」
としています。
つまり、ワキが締まっているとは
「 バックスイングからフォロースルーで、両肘がほぼ真下を向いている 」
ことと言えます。
スイング中のワキが締まっているゾーン
この位置では、ワキは締まっていることが望ましい
≪三角形のキープとは≫
「ワキが空いている」とは、スイング中の両肘が真下を向かず、
“外側に張っている”
ことを言います。
無理にトップの位置を大きく、高くしようとして、
肘が外側に張って五角形になってしまうくらいなら、
9時の位置までのトップの位置でも良いのです。
倶楽部ゴルフジョイのレッスンでは、
スイング中に腕と肩できる三角形は大小の2つあると考えます。
肩幅を底辺とし、両腕の長さを辺とする「大三角形」と、
両肘を結んだ線を底辺とし、肘から先を辺とする「小三角形」です。
大三角形のキープは、およそ腕が腰から腰の8時~4時の範囲までです。
小三角形のキープは、両肘の間隔が、
トップ~ダウンスイング~フォロースルーまでほぼ同じであれば、
スイング中の三角形はキープされていると言えます。
9時の位置以降と、3時の位置以降は、大三角形は崩れます。
つまり、構えたときの両肘の間隔がスイング中終始同じであれば、
大小の三角形のいずれかがキープされているということになります。
≪三角形を保つとは、ひじを縦にたたむこと≫
スイング中の肘は、タテにたたむということが、
三角形を崩さないということなのです。
ここを誤解すると、テークバックで両腕を伸ばしたまま
どこまでも上げようとしてしまいます。
これでは、スイングを崩してしまい変則スイングとなってしまいます。
当然、ワキは空いてしまいます。
「肘をタテにたたむ」とは、スイング中の両ひじは身体の幅の中にあることなのです。
「肘をタテにたたむ」とは、スイング中の両ひじは身体の幅の中にあること
≪まとめ≫
レッスン記事等で、
「バックスイングはできるだけ身体から遠くへクラブを上げる」
「両腕の三角形を崩すな」
などの用語にはまどわされないようにしてください。
身体の柔軟性が高いジュニアゴルファーやプロゴルファーなら可能かもしれませんが、
アベレージゴルファーには適さないでしょう。
良いスイングは、良いアドレスから生まれることは、先に述べてきました。
良いスイングは、スイング中に「ワキを締めろ」というような
“ああしよう、こうしよう”という操作が少なくなります。
私のスイング作りの目指す考え方です。
あなたの100切り達成を心から応援しします!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法23
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
バックスイングは肩をしっかり回すな(その1)
レッスンを受けている、受けた経験がある方で、
「バックスイングでは、肩をしっかり回せ」
「もっと肩を深く入れて!」
と言われたことがない人は、いないのではないでしょうか。
ゴルフの本を読んでもそう書いてあるし、
仲間同士練習場で教え合っている場面でも、
よく耳にする表現です。
「肩をしっかり回せ」という表現からは、
ダイナミックなフォームが連想され、
さらには、大きな飛距離が出せるイメージになりそうです。
また、
「バックスイングでは、
肩は90度以上、腰は30度程度回せ」
とも言われているようです。
☆★“その定説”を徹底検証する☆★
“肩自体が回る角度”をご存じでしょうか?
ちょっと実験です。
腰から下は、できるだけ回らないように固定して、肩のみを回してみてください。
ふつうの柔軟性の持ち主なら、
肩自体は20度くらいしか回らないのではないでしょうか。
「肩をしっかり回そう」とすると、
意識は「肩」という単語のみに反応し、
“肩だけを回そう”
としてしまうものです。
となると、腕にばかり力が入ってしまうはずです。
よく、聞くのは、
飛ばしのパワーを溜めるには、
下半身はできるだけ動かさず、上半身とのねじれ差を作れ
という表現です。しかし、そんな動きは、プロゴルファーか、
アスリートゴルファーレベルの人くらいにしかできないことでしょう。
下半身をしっかり固定し、
腕の強い引っ張りで肩を回したバックスイングは、
見た目にはパワフルなトップの形になりそうです。
この定説を信じているゴルファーは、
「肩は90度以上回して」
と、知識としては知っているので、
肩を一生懸命に回そうと頑張ります。
肩自体は20度位しか回らないのに・・・。
下半身を動かすまいと踏ん張りながら腕の力だけで、
下半身をねじっていることになりますから、
肩にもかなり力が入り、スイングでは好ましくない、
“いかり肩”になってしまいます。
車に例えれば、ブレーキを踏みながら、アクセルを吹かしている状態です。
ダウンスイングではガクンと右肩が下がり、ダフったり、それを避けたりして
伸び上がってしまうミスになるでしょう。
↓ ↓ ↓
~つづく
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法22
バックスイングの左腕は、まっすぐに伸ばすべきなのか?
100切りにお悩みのゴルファーのみなさんの、
バックスイングからトップの位置までの左腕は、どのような状態でしょうか?
雑誌やテレビ中継で観る今人気の選手のバックスイングから
トップの位置までの左腕は、ビシッと伸びてカッコいいです。
松山英樹選手や石川遼選手も、スッと左腕が伸びていますね。
一般的には、
「バックスイングの左腕はしっかり伸ばせ」
と、定説のごとく伝わっているようです。
ゴルファー同士のゴルフ談議や教え合っている風景を見ていても、
「左腕はまっすぐに伸ばして!」
との声がよく聞かれます。
私も日々のレッスンで、
「バックスイングで左腕が伸びないのだけど、どうしたら伸びるのか?」
を聴かれないことがないくらい、この質問を受けます。
☆★“その定説”を徹底検証する☆★
多くのゴルファーの理解として,
「左腕をしっかり伸ばせ」
というと、
「ピンと突っ張る」
ことになってしまうのではないでしょうか?
私のレッスン経験でも、左腕は
“伸ばさなければならない”
と思い込んでいる人が圧倒的に多いという実感です。
左腕をピンと突っ張った状態で、わずか数センチ大のボールをきれいに打てるでしょうか?
関節をピンと突っ張ることは、手先の感覚を鈍くし、腕の力も落としてしまいます。
例えば、腕をピンと突っ張っては、重いものは振りにくいし、
ピンと突っ張ってクラブを振ってみると、全くスピードが上がりません。
重い物を、
【上の画像】 腕を伸ばして振る
【下の画像】 腕をたたんで振る
ちょっと実験です。
クラブを逆さに持ってスイングしてみてください。
すぐに違いがわかることでしょう。
バックスイングで左腕をピンと伸ばそうとする人は、
フォロースル―でも腕を伸ばそうとするものです。
腕は短く使った方が、圧倒的にヘッドスピードが上がります。
≪腕を伸ばした状態とは?≫
ゴルフスイングにおける、「腕を伸ばした」状態を考えてみましょう。
腕の関節は、ごく自然にダランと垂らした状態では、軽い「くの字」になっています。
これが腕の「伸びている」状態です。
多くのゴルファーは、バックスイングで、
「腕を伸ばした」=「腕を突っ張る」
と解釈しているのではないでしょうか?
腕(肘)を突っ張ってしまうと、腕全体の感覚が大きく落ちて
バックスイングからトップにかけて相当苦痛を感じることでしょう。
この状態でわずか数センチ大のボールをきれいに打てるのでしょうか・・・。
ゴルフ雑誌で「プロの身体測定」の記事で見たのですが、
松山英樹選手、石川遼選手ともに、肩の関節は異様とも言えるほど柔らかいです。
他のプロゴルファーも、両選手に近いものがありました。
ゴルフ的には、
「肩の可動域が広い」
と表現されています。
一般的なアマチュアゴルファーの柔軟性とは、比較にならないでしょう。
≪左腕の感覚が鈍くなる例≫
ホワイトボードに字を書く際に、肘をピンと突っ張って書けるでしょうか。
適度にヒジを曲げるはずです。
この場合は右腕となりますが、意味は解かっていただけると思います。
このように、腕(ヒジ)の関節は、適度に曲げている方が、
適正な使い方ができるものなのです。
ヒジをピンと突っ張ると、
手首の動きや滑らかさが大きく制限され、
操作性が著しく落ちます。
ダフったりトップしたりで、球をスクエアにとらえることが難しくなります。
さらに、インパクトゾーンで必要なスナップを利かせられません。
思ったようにスイングできないゴルファーのほとんどが、
バックスイングの左腕は突っ張るものと思い込んでいます。
もしあなたが、このタイプなら、ここで選択をしてみましょう。
◆ストレッチを取り入れ柔軟性のアップに努めるか
または、
◆腕は曲がっていてもオッケーとして、そのままでスイング作りを続けていく
私が主催している、「目指せ!100切り達成講座」を受講していただいている方たちには、
「左腕は曲がっていても問題ありませんよ」
とアドバイスしています。
上記の身体の使い方や意味を説明すると、深く納得していただけるようです。
左腕は曲げたままでもOKと、ご自分の柔軟性に合ったスイング作りにとりかかると、
すぐに、一気に上達していきました。
もちろんその後、見事に100切りを達成したことは言うまでもありません。
スイングに悩んでいるゴルファーは、左腕を何とか伸ばそうと頑張るようです。
しかしストレッチはあまりやりませんが・・・。
となると、できないことは、それはそれで「受け入れる」思考の
柔軟さが、上達のポイントになりそうです。
※ 以下のページを参考にしてみてください。
≪バックスイングでの左腕の伸びは個人差による。
柔軟性に乏しいゴルファーは、
むしろ左腕を軽く曲げてバックスイングしていく≫
バックスイングの左腕が伸びるかどうかのチェックの方法をお教えしましょう。
右腕を背中に回し、左腕一本でバックスイングしてみてください。
これ以上左腕が上がらない位置で、右手を付けた形があなたのバックスイングの適正な形です。
左腕一本でバックスイングしていくと、小手先では上がっていきません。
ボディーでしっかりねじらないと、肩もほとんど回らず、とても低い
位置のトップになってしまうでしょう。
≪100切りがラクラク達成できるあなた流スイングへの転換のコツ≫
ストレッチの項目の、
「両手を頭の上で伸ばして合わせる」
で、腕が真っ直ぐに伸びない人は、残念ながら、バックスイングでも左腕はビシッとは伸びないでしょう。
これは、あくまで現時点であって、ストレッチの継続で、
伸ばせる可能性が芽生えてくる、また伸ばせるように目指すことが大事ではないのでしょうか。
スイング作りにおいて、
■「左腕が曲がっているデメリットはない」
■「無理に伸ばすメリットもない。インパクトで伸びていれば良い」
と考えてください。
柔軟性の低いゴルファーが、左腕を無理に伸ばそうとするなら、
むしろデメリットになると、私は考えています。
プロのスイングは、左腕は真っ直ぐ伸びてはいますが、
決してピンと突っ張っているわけではありません。
プロでも、バックスイングで左腕が曲がっている人は多数いますし、
シニアのプロになると、ほとんどが曲がっています。
よほど柔軟性に富んでいるゴルファー以外は、
バックスイングでの左腕は、ゆとりを持たせたほうが、身体はよくねじれるはずです。
まとめますと、
バックスイングでの左腕の伸び具合は個人差による。
柔軟性に乏しいゴルファーは、左腕はむしろ軽く曲げるくらいで良い。
となります。左腕は、ダウンスイングで振りおろしてくる勢いで、
自然にアドレス時の長さに伸びていきます。
そのためには、グリップや肘に力が入らないように意識しておくことです。
ゴルフスイングの見栄えの美しさは、
「柔軟性の高さに比例する」
といっていいでしょう。
☆★上達につながる正しい理解☆★
簡単なチェックをしてみましょう。
バックスイング~トップの形を作り、
5秒間以上静止できる状態での左腕の曲がり具合が、
現在のあなたのバックスイングの適正な形です。
無理をして左腕を突っ張って見た目のカッコよさを追求するか、
左腕が多少曲がっていても、確実にボールに当たるスイングにするかを選択するのは、
ゴルファー一人一人の考えによるでしょう。
バックスイングで左腕がきれいに伸びるゴルファーは、
そもそも最初からそんなことを意識しないくらい柔らかいものです。
ほとんどが、ジュニアゴルファーか、若手のプロゴルファーでしょう。
“伸ばさなければ”と思った時点で、伸ばせるタイプではない、と考えるのが無難です。
スイング作りでは、「~しなければならない」や「~してはならない」ことはほとんどありません。
個人差を知り、自分の適正を見つけることで、あなたのスイング力はまだまだアップしていくことでしょう。
<今回のまとめ>
バックスイングで、左腕にゆとりをもたせると、
テレビで観るプロゴルファーの華麗なフォームと比較すれば、
残念ながら、どうしても見劣りしてしまいますが、
「左腕を軽く曲げてバックスイングしていく」
を理解して自分なりに取り入れていった方は、
飛躍的にレベルアップしました。
身体が硬いゴルファーの方は、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法19
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
コースでのレッスンのご案内はこちら ⇒ クリック
バンカーショットが簡単に打てる これで100切り達成だ!
100切りで悩んでいるゴルファーの苦手項目の一つに、
バンカーショットが挙げられます。
ふだん練習場でもなかなか練習できないので、
技術が習得しづらいのは仕方ないかもしれません。
しかし、そういったハンデがある分、
打ち方の理論や知識は備えておくべきです。
100切り達成をわずか2~3打で逃してしまった理由として
「バンカーから出すのに3回もかかってしまった」
「バンカーからホームランしてOBになってしまった」
等、よく聞く話です。おもしろいもので、逃げれば逃げるほど、
なぜかつかまってしまうのがバンカーなのは経験済みでしょう。
バンカーショットは、フェースを開いたりスタンスを変えたりと、
何やら難しそうな打ち方と思われているようです。
本項目では、高度な打ち方は後回しにして、
100切り達成のためのバンカーショットの打ち方を見ていきましょう。
《ここが我流スイングへの落とし穴だった!》
なぜバンカーショットが苦手になってしまったのでしょうか?
私の実感では、バンカーショットの定番理論である
「オープンスタンスとオープンフェース」
が習得できず、また理解にも努めなかったことが原因です。
サンドウェッジの特徴であるバウンス機能(砂を弾いて潜らない)も知ってはいるが、
発揮できるまで至っていない。加えて練習不足とくれば、
バンカーショットの失敗を重ねてしまい、
強い苦手意識がついてしまうのは当然です。
サンドウェッジのバウンスは、オープンフェースにしないとうまく機能せず、
オープンスタンスで目標に対してアウトサイド~インサイド軌道で
スイングしないと方向性が出せません。
さらにやっかいなのが、砂質の見きわめができないと、
バウンス機能がかえってマイナスに働いてしまうことです。
砂がフカフカでなければ、バウンス機能はかえってじゃまになってしまうからです。
昨今のゴルフ場の通常営業では、トーナメントで見るようなフカフカのバンカーは希少で、
砂は少なめで固くしまっている傾向です。
砂質の見きわめやバウンス機能の感覚がつかめる前に失敗が先立てば、
苦手意識だけが強くなり、
我流スイングのバンカーショットになってしまうのは残念です。
自分流スイングへの転換のコツ
100切り達成のためのバンカーショットは、
1発で脱出できて2パット圏内によれば充分合格といえます。
自分流スイングのバンカーショットでは、
よりやさしい打ち方で、確実にバンカーから脱出することを目指します。
とにかくバンカーから1発で出せればいいだけなら、
スクエアフェースとスクエアスタンスで、身長程度の土手は充分越せる高さを出せます。
バンカーショットもアドレスが重要です。
“うまくダフる”ために、ヒザを深めに曲げ、腕の動き主体のスイングをします。
芝からのショットに比べて、身体の回転は少なめでフットワークは抑え気味にします。
《正しい解釈のポイント》
バンカーショットの一番のポイントは
「球は打たないで砂を打つ」
ことです。スクエアフェースとスクエアスタンスなら、
バウンス機能はわずかしか働かないので、確実にダフれます。
構え方と打ち方はアプローチとほぼ同じですが、砂の抵抗があるので、
アプローチショットの3~5倍飛ばすイメージでショットします。
しかし、バンカーショットが苦手なゴルファーにとって、
それだけ振るのはかなりの恐怖心があるでしょう。
サンドウェッジの機能の知識や、よりやさしい打ち方を目指す
自分流スイングのバンカーショットの理解が、その恐怖心を勇気に変えてくれるはずです。
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法18
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
100切り達成を可能にするフェアウェイウッドの知識と技術
100切りで悩んでいるゴルファーの多くは、フェアウェイウッドでのミスが多いようです。
逆に、フェアウェイウッドが使いこなせれば、100切り達成は、グッと近づくでしょう。
倶楽部ゴルフジョイの「100切り達成講座」でも、
フェアウェイウッドのレベルアップには、特に力を入れてレッスンしています。
狭いホールでは、ティショットでドライバーを使うのを止め、
フェアウェイウッドで攻めることで、リスクを大きく減らすことができる。
パー4、パー5のティショットは、常にドライバーという考えを変えてみましょう。
確実に大叩きは減るはずです。
≪フェアウェイウッドはダフリに強い≫
「滑らせるように打つ」とは?
フェアウェイウッドの構え方
アイアンとの構えと比較しておぼえておきましょう。
フェアウェイウッドの球の打ち出し角度
フェアウェイウッドの成功は、フィニッシュで決まる
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法17
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
ダウンスイングで"タメ"を作ろうとするとヘタになる(その2)
この戻す、コックをほどく動作がアンコックです。
切り返しで生まれたタメを、
「ギリギリまでほどかない」
ダウンスイングからクラブで
※ 画像をクリックすると、拡大されます。
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法15
ドライバーは"アッパー軌道"で振るな 2
■ 前回の復習
ドライバーショットは、クラブヘッドがスイング軌道の最下点を過ぎて、
上昇し始めた付近でアッパー軌道のインパクトで打つ。
そのため、球の位置は、左かかと延長線上付近に置くのが良いと言われている。
また、球をアッパー軌道でとらえるために、ティを高くしているゴルファーもいるが、注意が必要だ。
アッパー軌道が過度になると、スイングを崩してしまうことがあるからだ。
《自分流スイングへの転換のキモ》
「アッパー軌道で振る」と「アッパー軌道になる」の解釈で、スイング動作が変わってきます。
※スタンダードスイング理論では、スタンスの中央で
スイング軌道のほぼ最下点になるわけですから、
左足かかと内側付近にあるボールをとらえるときに、
“結果的に”アッパー軌道でとらえる “ことになります。
← 手元と身体から離れ過ぎるのはNGフォロースル―
過度のアッパー軌道で、下からカチあげるようにボールをとらえる動きは、
高い柔軟性と筋肉隆々の身体能力がなければ、
方向性を損ないパワーの伝導率も高くはありません。
自分流スイングでは、一発狙いのスイングは求めませんから、ティーアップはやや低めにします。
スイング軌道の最下点を意識しながらスイングするようになるので、
ダフりやテンプラが減りミート率が高まります。
自分流スイング作りでは、ドライバーの最高飛距離よりも平均飛距離がアップすることを目指します。
あくまで、スコアメイクを優先するからです。
※ 「自分流スイング」「我流スイング」の定義は、こちらの「スタンダードスイング理論」でご確認ください。
《正しい解釈のポイント》
ドライバーは、14本の中では一番シャフトが長く、ロフト角度も小さいので、
ナイススイングをすれば、一番「飛んでいく」クラブです。
もちろん、自分のヘッドスピードやミート率に合ったクラブでなければなりません。
ヘッドスピードが40以内のゴルファーなら、ロフト角は10~12度がおすすめです。
ティを低めにして、過度のアッパー軌道にならないようにスイングすれば、
「フェアウェイウッドの1番」
になり、打ちやすさが倍増します。
実際の弾道より低く飛んでいくイメージを持てば、不必要なアッパー軌道を防止し、
安定したドライバーショットが打てるようになります。
≪まとめ≫
■ ドライバーは、アッパー軌道で打てば、打ち出し角度も高くなりキャリーが稼げて飛距離アップが望める。
■ アッパー軌道でのインパクトは、球の位置やスタンス幅、ティの高さなどを考えること。
■ 「アッパー軌道で振る」となると、過度にアッパーにしようとしてしまいがちだ。
「”結果的に”アッパー軌道になる」のが、ドライバーショットの良いスイングとなる。
■ 100切りを目指すスイング作りでは、「一発の飛び」は目指さない。
むしろ、ミスの少ない安定的な1打がほしい。
そのために、ティアップは、やや低めがおススメだ。
そのほうが、過度のアッパースイングを防げ、アイアンやフェアウェイウッドと同じ軌道で打てるからだ。
つまり、「フェアウェイウッドの1番」になるからだ。ロフト角も、10度以上はほしい。
了
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法14
ドライバーは、"アッパー軌道"で振るな!
この項目は、ドライバーの飛距離アップレッスンでは、定番中の定番です。
ゴルフ本でよく目にするのは、
「球の位置は左足かかと延長線上に置け」
とありますが、一般のゴルフ本や本項目と、
私が提唱するスタンダードスイング理論との比較をしながら見ていきましょう。
※ 「自分流スイングと「我流スイング」の違いが説明してありますので、ご覧ください。
《ここが我流スイングへの落とし穴だった!》
「アッパー軌道でインパクト」とセットになるのが、高いティアップです。
飛ばし屋の最高峰と言えるドラコン選手がものすごく高いティアップをしているので、真似をするゴルファーが多いようです。
ティアップが高いと「飛ばしてやる~!」という気持ちが高まってきます。
ドラコン選手で特徴的なのは、広いスタンス幅と、
強いフックグリップでかなりのアッパー軌道で高く打ち出して飛ばすという打ち方です。
ドラコン競技の形式はご存じでしょうか?
6回打って、フェアウェイに飛んだ1番飛んだ球が採用されます。
これは、私たちスコアを求めるゴルファーが目指すスイングとは明らかに違います。
たとえミスショットだろうと、打ってしまったら、1打として数えなければならないのがゴルフプレーです。
スコアメイクを基準に置いた「ゴルフプレー」用のスイング作りと、
6分の1発狙いの「ドラコン競技」用のギャンブル的スイングの違いと言えます。
ドラコン選手は、飛ばすためにあらゆるミスを想定して練習しているはずですが、
アマチュアゴルファーが安易に真似をするには危険過ぎます。
過度のアッパーに振りぬこうとすると、
結果的に右肩が大きく下がってしまい、
身体の回転ができず、
インパクトの前に地面を叩きやすくなったり、
カチ上げるようなフォロースル―になってしまうでしょう。
こんなことを繰り返していては、
我流スイングを固めてしまうことになります。
← こんなフォロースル―の形はNGです。
~つづく
100切りを最短で達成するスイング理論(各パートの標準形)
100切りを最短で達成する考え方や知識
スタンダードスイングの各パートの標準形を知る
スタンダードスイングのアドレスからフィニッシュまでの7つのパートの部位に分けて、特徴を説明していきます。
スタンダードスイング理論は
「良いスイングは、良いアドレスから生まれる」
ことを根本的な考え方とします。
「良いアドレス」を1つ目のパートとします。
良いアドレスを作るためには、4つの項目を守りましょう。
最後にクラブごとの球の位置は適正か、です。
昔から、
「構えを見れば、打たなくてもその人の腕前がわかってしまう」
と言われています。
私は、「これから打つショットの運命は、8割以上決まっている」と考えています。
つまり、アドレス次第で、ナイスショットかミスショットかが、ほぼ決まってしまうということです。
体重は徐々に右足に乗っていきます。手元が肩の位置では、コックは完全に完了します。
3つ目のパートはトップ・オブ・スイングです。
4つ目のパートはダウンスイングです。
切り返しと呼ばれるダウンスイングの始動は、左足と腰がやや先行していきます。
上半身と下半身のズレが生まれ、体重は左足に乗っていこうとしています。
バックスイングで準備したパワーを解放し、球に伝えていく動作がアンコックです。
ここでは、アンコック(腕とシャフトとの間にできた角度をほどく)前の位置と、
アンコック後の位置の2段階に分けています。
アンコック前では、まだクラブヘッドは上空を指し、アンコック後の手元の位置と角度は、
バックスイングの腰の位置(左腕が8時)とほぼ同じが理想です。
5つ目のパートはインパクトです。
顔は打つ人から見て球の右に位置するのが理想で、この形はビハインド・ザ・ボールと呼ばれています。
手元はほぼアドレスの位置に戻り、目標側に流れていません(身体の幅の中にある)。
下半身からダウンスイングできれば、アドレス時よりも腰は目標側に向き、
わずかにハンドファーストの角度が強まり、球にしっかりとパワーが伝わっていきます。
右ヒザと右肩も著しく前へ出ないことがポイントです。
6つ目のパートはフォロースルーです。
グリップが腰の位置(4時の位置)と肩の位置との2段階に分けています。
手元を身体から離していかないことがポイントです。
グリップが腰の位置では、バックスイングでのグリップが腰の位置とほぼ左右対称です。
7つ目のパート、最後にフィニッシュです。
「構えと終わりが良ければ、途中も良し」と述べたように、
スタンダードスイング理論では、フィニッシュは、
アドレスとともにとても重要な位置とします。
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法13
100切り、シングルまで可能な「スタンダードスイング理論」
100切り達成可能なスイングの基準を作る、スタンダードスイング理論
~あっという間に100切り達成!~
~ シングルハンディにだって、十分到達できる ~
スタンダードスイングとは、
「多数の良いスイングの各パートの標準形や平均値(こちらで詳説)」
で作られた、いわばスイングの理想形です。
≪自分流スイングと我流スイング≫
「100切り達成講座」では、スタンダードスイングを8つのパートに分けて学んでいきます。
各パートの形(別途詳細)のポイントや理解をベースに、
各自の身体能力やクセを活かしたりアレンジしてスイングを作っていきます。
そうやって作りあげたスイングを自分流スイング(または、あなた流スイング)と呼ぶこととします。
一方、スタンダードスイング理論を正しく解釈せず、
ただやみくもに球を打ってでき上がったものを我流スイングと呼ぶこととします。
自分流スイングは、
① 自分の身体能力に応じて作り上げたので、迷いなく思い切って振れます。
② スタンダードスイングからのアレンジだから、エラーの箇所やその原因は、
スタンダードスイングに照らせば、発見が容易で修正が可能です。
③ 自分の個性や特徴を理解して作りあげたスイングなので、緊張下で強いのです。
我流スイングは、
① よりどころ、およびベースとなる動きや考え方がありません。
② よってスイングのエラーの原因がわからず、直しにくい。
③ 調子の波が大きく、いつも不安を感じながら振らなければなりません。
自分流スイングは、スイング理論の標準値・平均値であるスタンダードスイングから、
「どこかの部位で許容範囲内でのズレやエラーがあるスイング」
と言えます。
一方の我流スイングは、
「自分流スイングよりもエラーの動きが過度で形成されたスイング」
であると言えるでしょう。
そうなった理由は、スイング理論や正しい動作の理解不足、
スイングに必要な柔軟性や可動域の不足、違和感(正しい動きの正しい感覚)の拒否等と思われます。
≪自分流スイングで100切り達成を≫
「100切り達成講座」は、プロのような美しいフォームや豪快なスイング作りが目的ではありません。
現時点のあなたのスイングをアレンジして100切り可能なスイングにレベルアップすることを目指します。
あなたの現在のスイングが、
■ スタンダードスイングからどれだけズレているか
■ どの程度までが許容範囲か
を見きわめ、自分の能力やクセに応じて改善していただきたいのです。
100切りで悩んでいるゴルファーの10人のうち9人までが、適さない考え方や誤った解釈をしています。本講座は、「10人のうちの1人」の“抜けがけ”上達へと導く内容です。
あなたの身体能力、ゴルフの環境などを考慮し、
「あなたによる、あなた専用」
の自分流スイングを作って、今こそ、100切りを達成しませんか?
あなたの100切り達成を心から応援しています!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法12
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
「下半身の安定」は、べた足にすることではない 2
「下半身の安定」は、ベタ足にすることではない
~1の続きから
《 スエ―とスイング軸とは 》
左かかとを、ヒールダウンさせると同時にダウンスイングを開始すれば、
下半身から順番に動かせて、スイングのリズムもタイミングも良くなってきます。
よって、倶楽部ゴルフジョイでお教えしているスイング作りでは、
「バックスイングで左足かかとをべた足にするメリットはない」
と考え、ヒールアップを推奨します。
極端にヒールアップするのではなく、球1個分程度で十分です。
左ヒザは前方に突き出さず、内股に使っていきます。
ヒールアップしたトップの位置で3秒程静止してみてください。
腕でクラブを引っ張りあげず、上半身や腕をリラックスさせることも忘れないようにしましょう。
この状態から、左足かかとをドンと踏み込めば、必ず腕が勝手に下りてきます。
結果的に、ダウンスイングは適度なインサイドから下りてきて身体のターンもスムーズになります。
《 正しい解釈へのポイント 》
特にフォロースル―においてのベタ足とは、ほんの一瞬であり、
ずっとキープすることではありません。
高速度カメラで撮られた連続写真の、その一瞬だけを見ていたら、理解を誤ります。
べた足タイプのスイングとは、
「ベタ足の状態や期間が長いタイプか短いタイプか」
に分かれるだけです。
特に飛ばし屋タイプでは、インパクトゾーンで右足を
ベタ足にしていることは、ほぼありません。
スイング中のエックス脚をキープして、一気に右足をターンして飛ばしていきましょう!
もちろん、べた足で上手く打てている人は、そのままでOKです。
柔軟性に富んでいるか、腕の使い方が上手なゴルファーなのでしょう。
ここでの解釈で大事なのは、
「べた足でなければならない」
や
「ヒールアップしてはならない」
といった“限定”はよくないということです。
自分の特徴や身体能力を見きわめ、適している方を採用することが
倶楽部ゴルフジョイが目指す100切り達成が可能なスイング作りなのです。
《 べた足のメリット 》
最後に、べた足が特に必要な場面をお教えしましょう。
傾斜地からのショットやバンカーショットです。
これらの場面では、スイング中終始ベタ足状態が必要です。
傾斜地やバンカーショットでのべた足スイングの腕の使い方は、
ヒジをコンパクトにたたみ、手首を柔らかく使うことです。
両足を閉じて、通常のアドレスよりもヒザを低く
落として連続素振りをしてみてください。
傾斜地やバンカーからの腕の使い方が上手になります。
また、スイング軸が安定し、バランス力がアップする一石二鳥の練習法です。
傾斜地ショットの直前に実践すれば、ナイスショットの確率が上がるはずです。
■ まとめ
ベタ足はスイングを安定させ、インパクトからフォロースルーにかけても、
右かかとはベタ足が良いと言われている。
一方、バックスイングの左ヒールアップは、
スエーや軸がブレると言われている。
しかし、ベタ足の意味を正しく理解していないと、
腕の動きが悪くなり、ミスショットになりやすい。
ベタ足スイングは、股関節の可動域の充分な広さが必要だ。
一般的なゴルファーで、その条件を備えている人は大変少ない。
そこで本メルマガでは、逆にヒールアップをお勧めする。
特に左ヒールアップは、バックスイングでしっかり
ねじれて肩が入り、良いトップが作れるし、
ダウンスイングからは、自然に下半身から始められ、
スイングのリズムやタイミングが良くなる。
スイング中、やや内股感覚を維持していれば、
軸ブレやスエーは充分防げ、
ヒールアップのデメリットは気にしなくても良い。
ベタ足が必要な状況は、傾斜地やバンカーショットである。
バランスが保ちにくいし、平地や芝の上からの通常のショットよりも、
少ないフットワークで済むからだ。
考え方として大事なのは、
「ベタ足にしなければならない」
「ヒールアップしてはならない」
といった「限定」は良くないということだ。
自分の身体的特長や能力を見きわめ、
ベタ足かヒールアップの適している方を選ぶのが賢明である。
了
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法11
「下半身の安定はベタ足にすることではない」1
(前半)
「スイングを安定させるには、
下半身の動きを抑えることだ」
「安定したショットをするには、
べた足にしろ」
と、よく耳にしませんか?
「バックスイングの左足かかと
ヒールアップは、軸がブレる」
などと言われています。
一方、インパクトから
フォロースル―にかけても、
右足はべた足が良いと
言われることもあり、
これも解釈が難しそうです。
今回は、
1. バッスイング、フォロースル―の
「ヒールアップ」と「べた足」の違い
2. そのメリットとデメリット
という視点で展開していきます。
《 NGスイングへの落とし穴 》
ゴルファーは、
「スイングが安定する」
や
「軸がブレない」
という言葉に弱いようです。
べた足(左かかと)で
バックスイングをするためには、
股関節の可動域の
充分な広さが必要です。
しかし、私のレッスン経験では、
アマチュアゴルファーで
必要な可動域を
備えている人は大変少ないです。
一方、フォロースル―での
べた足(右足の)を
正しく理解するには、
「べた足の状態」
や
「べた足の期間」
という目安が必要です。
アプローチショットは別ですが、
フォロースル―から
フィニッシュにかけて、
べた足のままのプロは皆無です。
ということは、いつか右足の
かかとは上げていかなければなりません。
「いつまで(期間)べた足の
ままでいいのか」
がわからないから、
「べた足」という一点に意識が
ロックされてしまい、
そのまま手だけでフィニッシュまで
振ってしまうのです。
これでは、身体の回転や腕の動きが
じゃまされ、ヘッドスピードが出せません。
「アクセルとブレーキを同時に踏んでいる」
ようなもので、NGスイングへと陥ってしまうはずです。
《 自分流スイングへの転換のコツ 》
ゴルフでは、完全ベタ足で
いいのは、パターだけです。
フォロースルーで右足のかかとは、
明らかに浮かないまでも
浮こうとしているのが正しい理解です。
フォロースルーで右かかとが
浮いていかないと、
スムーズな身体の回転ができません。
スイングでスムーズな
回転をするには、上半身ではなく
フットワークで回転していくのが
良いスイングであり、
正しくフットワークを使って
軸回転をすれば、安定した
インパクトが実現できます。
~後半へつづく
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
フィニッシュを決める
フェアウェイウッドの球の打ち出し角度
フェアウェイウッドの構え方と打ち方
フェアウェイウッドを滑らせるように打つとは?
フェアウェイウッドはダフリに強い
フェアウェイウッドを使いこなそう
100切りバンカーショット上達塾 身体の使い方のコツ
バンカーショットが上達できる、苦手を克服し100切りを達成できる!
バンカーショットが苦手で100切りできなかった方へ
いつもバンカーで大叩きして、惜しいところで100切りを逃がしていた方、あきらめないでください。
ここで紹介するレッスンは、バンカーショットが苦手な方が、見事克服していただいた要点やポイントをまとめてあります。
このページでしっかり予習して、コースでどんどん実践すれば、
バンカーショットは必ず克服でき、上達できることをお約束します。
コースでのレッスンのご案内はこちら ⇒ クリック
バンカーショットと通常のショットは少し違う
以下の充実したレッスンメニューもご覧ください
1.パター、アプローチ、バンカー専門レッスン
⇒ クリック
100切りには必ず必要なテクニック満載
2.プライベート・マンツーマンレッスン
⇒ クリック
超ぜいたくな、あなた一人のためのレッスン
3.まずは1DAYお試しレッスン
⇒ クリック
4.スイング診断・改良レッスン
⇒ クリック
”イケメンスイング” ”スイング美人” になれます!
あなたの100切り達成を応援します!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法10
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
バンカーショットはオールスクエアで打ってみましょう
100切りで悩んでいるゴルファーの苦手項目の一つに、バンカーショットが挙げられます。
ふだん練習場でもなかなか練習できないので、技術が習得しづらいのは仕方ないかもしれません。
しかし、そういったハンデがある分、打ち方の理論や知識は備えておくべきです。
100切り達成をわずか2~3打で逃してしまった理由として
「バンカーから出すのに3回もかかってしまった」
「バンカーからホームランしてOBになってしまった」
等、よく聞く話です。おもしろいもので、逃げれば逃げるほど、
なぜかつかまってしまうのがバンカーなのは経験済みでしょう。
バンカーショットは、フェースを開いたりスタンスを変えたりと、
何やら難しそうな打ち方と思われているようです。
本項目では、高度な打ち方は後回しにして、
100切り達成のためのバンカーショットの打ち方を見ていきましょう。
《ここが我流スイングへの落とし穴だった!》
なぜバンカーショットが苦手になってしまったのでしょうか?
私の実感では、バンカーショットの定番理論である
「オープンスタンスとオープンフェース」
が習得できず、また理解にも努めなかったことが原因です。
サンドウェッジの特徴であるバウンス機能(砂を弾いて潜らない)も知ってはいるが、
発揮できるまで至っていない。加えて練習不足とくれば、
バンカーショットの失敗を重ねてしまい、
強い苦手意識がついてしまうのは当然です。
サンドウェッジのバウンスは、オープンフェースにしないとうまく機能せず、
オープンスタンスで目標に対してアウトサイド~インサイド軌道で
スイングしないと方向性が出せません。
さらにやっかいなのが、砂質の見きわめができないと、
バウンス機能がかえってマイナスに働いてしまうことです。
砂がフカフカでなければ、バウンス機能はかえってじゃまになってしまうからです。
昨今のゴルフ場の通常営業では、トーナメントで見るようなフカフカのバンカーは希少で、
砂は少なめで固くしまっている傾向です。
砂質の見きわめやバウンス機能の感覚がつかめる前に失敗が先立てば、
苦手意識だけが強くなり、
我流スイングのバンカーショットになってしまうのは残念です。
自分流スイングへの転換のコツ
100切り達成のためのバンカーショットは、1発で脱出できて2パット圏内によれば充分合格といえます。
自分流スイングのバンカーショットでは、
よりやさしい打ち方で、確実にバンカーから脱出することを目指します。
とにかくバンカーから1発で出せればいいだけなら、
スクエアフェースとスクエアスタンスで、身長程度の土手は充分越せる高さを出せます。
バンカーショットもアドレスが重要です。
“うまくダフる”ために、ヒザを深めに曲げ、腕の動き主体のスイングをします。
芝からのショットに比べて、身体の回転は少なめでフットワークは抑え気味にします。
《正しい解釈のポイント》
バンカーショットの一番のポイントは
「球は打たないで砂を打つ」
ことです。スクエアフェースとスクエアスタンスなら、
バウンス機能はわずかしか働かないので、確実にダフれます。
構え方と打ち方はアプローチとほぼ同じですが、砂の抵抗があるので、
アプローチショットの3~5倍飛ばすイメージでショットします。
しかし、バンカーショットが苦手なゴルファーにとって、
それだけ振るのはかなりの恐怖心があるでしょう。
サンドウェッジの機能の知識や、よりやさしい打ち方を目指す
自分流スイングのバンカーショットの理解が、その恐怖心を勇気に変えてくれるはずです。
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
100切りを最短で達成するスイング作りと練習法9
~シングルハンディ、競技ゴルファーにも効果的~
コースでのレッスンのご案内はこちら ⇒ クリック
サンドウェッジのバウンス機能とオープン理論
前回の記事では、
「100切りレベルのバンカーショットで、出すだけに徹するのであれば、
サンドウェッジのフェースやスタンスは開かなくても良い」
というお話をしました。
しかし、それではもの足りないという方には、以下の解説を参考にしてください。
≪サンドウェッジのバウンス機能とオープン理論≫
バンカー内の砂が、フカフカで柔らかい場合は、サンドウェッジのバウンス機能を使いましょう。
フェースをやや開くことによって、この機能が使えます。
≪オープン理論とは≫
スタンスは目標の左に向け(オープンスタンス)、フェースは目標の左に向ける。
スタンスに平行にスイングしていくが、フェースが右を向いている(オープン)ので、球は左には飛ばない。
サンドウェッジのバウンス機能とオープン理論は、砂が柔らかく、
フカフカ状態で適用される場合がほとんどです。
この「砂質の見きわめ」は、経験によるところが大きいので、
以下の記事も参考にして、バンカーショットをマスターしてください。
倶楽部ゴルフジョイの「100切り達成講座」では、
バンカーショットが苦手で100切りに困っている方に、
確実にマスターしていただけるカリキュラムをご用意しています。
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
SWのオープン理論
前傾角度とライ角度の比較
スイング軌道の角度(傾き度合い)の変化
美しく、飛んで曲がらないゴルフスイングを作るストレッチ
初心者~中級者ゴルファーが早く上達できる秘訣です
ゴルフスイングは、形だけを真似ようとしても、とても真似できるものではありません。
「関節の可動域」の広さ、つまり柔軟性をアップすることが、上達の近道なのです。
何も、体操選手のような柔軟性を身につけよ、というのではありません。
ゴルフスイングだけに使う、日常では使わない部位や、動作をスムーズにするために、
毎日ほんの少しのストレッチをするだけで、見違えるように上達できます。
以下に紹介するストレッチは、ゴルフスイング上達に直結するストレッチです。
倶楽部ゴルフジョイでは、
女性は、「スイング美人」に、
男性は、「イケメンスイング」に
なれるよう、スイングのレッスンをしていきます。
●ストレッチの基本4ポイント
■ 痛くなる手前の「痛気持ちいい」感覚が目安
■ きつくなると同時に、ゆっくり息を吐いていく
■ 無理して押し込んだり(できる範囲で可)、勢いをつけたりしない(痛める元)
■ ゆっくり、リズムよく(※1つの動作に20~40秒かけるのが理想的と言われている)
●スイングに特に必要な3部位に大分類
1.肩のストレッチ
■ スイング中腕がしっかり伸びるようになりフォームが美しくなる
2.股関節のストレッチ
■ バックスイングでしっかり股関節をねじることができる。
■ フォロースルーからキレのあるボディターンができるようになる。
3.足首のストレッチ
■ ボディターンで生まれる体重移動を、軸をブラさずに受け止めることができる。
以下に、動作の説明画像がございます。
まずは、3カ月取り組んでみてください。
必ず、スイングが良くなります。
■ スイングに必要な柔軟性をチェックする ⇒ こちら
■ 下半身の柔軟性のチェックとトレーニング方法 ⇒ こちら
■ 上半身の柔軟性のチェックと柔軟性アップのトレーニング法 ⇒ こちら
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!
スイングの始動のテクニックの例
バックスイングの始動の"きっかけ"を作る
完全に静止した状態からバックスイングを始めると?
アドレスでジッと固まってしまうのはNG
バックスイングを遠くへ上げるって??
100切り達成を最短で達成するスイング作り2
100切りを最短で達成するスイング作り1
スイング中の両ヒジは真下を向く
100切りが最短で達成できるスイング作り3
100切りが最短で達成できるスイング作り4
100切りを最短で達成するスイング作り5
100切りが最短で達成できるスイング作り6
100切りが最短で達成できるスイング作り7
バックスイングの良い作り方
バックスイングは、脚を使って作りましょう
バックスイングの肩の回転量
バックスイングの形の比較
肩をしっかり回したバックスイングって??
バックスイングのNG例
バックスイング・トップの形
バックスイングの左腕は伸ばすの?
100切りを最短で達成するテクニックと練習法
バックスイングの左腕が伸びるかどうかのチェックの方法
右腕を背中に回し、左腕一本で
バックスイングしてみてください。
これ以上左腕が上がらない位置で、
右手を付けた形があなたの
バックスイングの適正な形です。
左腕一本でバックスイングしていくと、
小手先では上がっていきません。
ボディーでしっかりねじらないと、
肩もほとんど回らず、とても低い
位置のトップになってしまうでしょう。
≪100切りがラクラク達成できるあなた流スイングへの転換のコツ≫
ストレッチの項目の、
「両手を頭の上で伸ばして合わせる」
で、腕が真っ直ぐに伸びない人は、
残念ながら、バックスイングでも
左腕はビシッとは伸びないでしょう。
■ 上半身の柔軟性のチェック法と柔軟性アップのトレーニング
https://www.club-golfjoy.com/contents/2017/08/post-236.php
これは、あくまで現時点であって、
ストレッチの継続で、
伸ばせる可能性が芽生えてくる、
また伸ばせるように目指すことが
大事ではないのでしょうか。
あなたの100切り達成を心から応援します!
こちらもご覧ください
 クリック!
クリック!